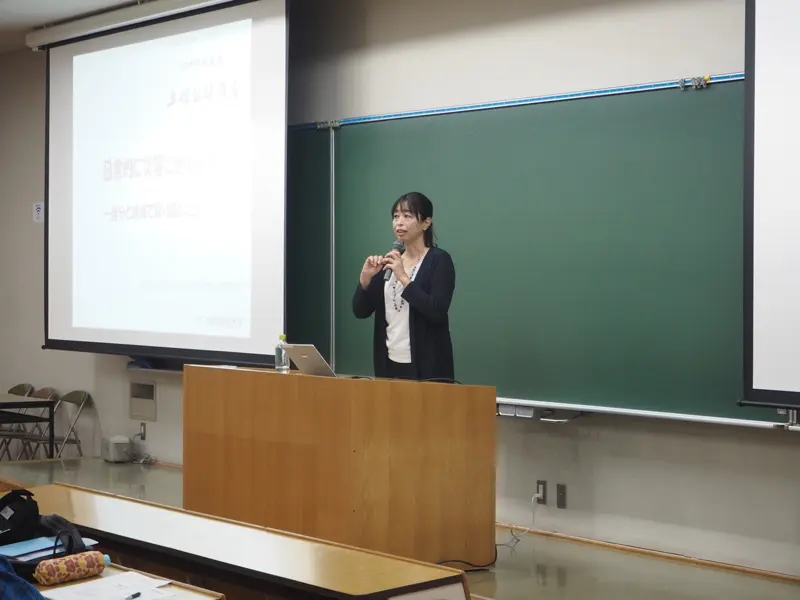土曜公開講座「日常的に災害にそなえる-自分と地域で取り組むこと-」を開催しました
2024/05/29
今春の土曜公開講座は第87回となり、「私たちのくらしと文化」という統一テーマに基づき、各研究分野の教員が全5回の講義を行います。
5月25日は有瀬キャンパスで現代社会学部 社会防災学科の伊藤 亜都子教授による土曜公開講座「日常的に災害にそなえる-自分と地域で取り組むこと-」を開催し、89人が参加しました。
伊藤教授ははじめに災害の定義について「災害は、地震や豪雨など自然現象、さらには新型コロナウイルスやテロなどを含めた『被害』をいいます。そのため、砂漠の真ん中などで大きな地震があっても、周囲に誰も生活しておらず『被害』が出ていなければ災害とは呼びません」と説明しました。
加えて「災害は社会的に弱いところを襲うといい、高齢化が進んでいる地域や老朽化した建物が多い地域などに被害が多く出ることが予想されます。また、都市部においても帰宅困難者の発生や、ライフラインの停止などの『被害』が懸念され、日頃から弱い部分を改善することで、災害時にも強い社会づくりを行うことが大切である」と伝えました。
次に阪神・淡路大震災における具体的なエピソードを交えて、避難所や医療現場の環境が悪かったことで災害関連死につながるケースがあることやトイレの不足により飲料を控えて体調が悪化すること、車中泊や避難所で長時間あまり動かないことから発症するエコノミークラス症候群などが懸念されることなど、避難所で発生する物資やトイレの問題を挙げ、これらは社会的な問題であり、環境を改善することで防ぐ必要があると話しました。
続いて、地域防災やコミュニティの重要性について説明しました。
災害発生時には自衛隊などの「公助」に時間がかかる場合があります。自分を守るためには、まず「自助」が重要であること。また、家族や近隣の人たちに救出される「共助」も多く、日頃の挨拶などから繋がりを作っておくことが大切です。
地域の防災力を高めるために、本来防災活動ではない地域活動に防災の要素を盛り込む手法があります。例えば、学校の運動会や地域の夏まつりなどに防災のエッセンスを加えることで、いつも決まった人しか参加しないことを防ぐことができます。平常時から自分事として災害に備え、地域でのネットワークを作ることで防災に強い地域社会がつくられます。
後半は、参加者が災害対応を自らの問題として考え、YesかNoのカードを使ってさまざまな意見や価値観を共有する防災ゲーム「クロスロード」を実施しました。
『避難所にて水も食料も持たない人が多数いる中、自分が持っている非常持ち出し袋を開けるか』という問題では、「そのような状況ではトラブルになりかねない」「せっかく準備していた食料を無駄にすることはない」などの意見があり、回答がほぼ半分に分かれました。また、この問題の解決策としては、「各々が非常持ち出し袋を準備しておくこと」「避難先にも十分な備蓄を備えておくこと」などの方法が挙がりました。
「クロスロード」ではこのように判断に迷う問題をいくつか出題し、実際目の前にないものに対してリアリティをもって考える想像力や、マニュアル通りではなく状況に合わせて自分たちで判断する創造力が大切だと伝えました。
受講者からは「被災したときどのように行動すべきか考えるきっかけになった」「普段からの備えを再考させられた」など多くの感想が寄せられました。
次回6月8日の土曜公開講座は、経営学部の石賀 和義(いしが かずよし)教授による「私たちのくらしとお金」です。