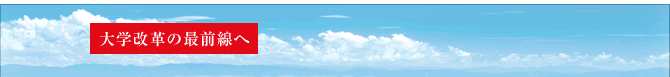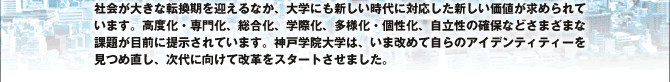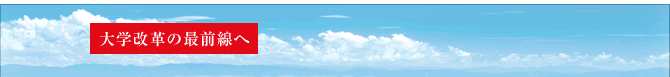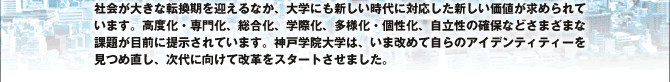|
 |
 |
| |
 |
| |
1995年1月17日、未曾有の災害をもたらした阪神・淡路大震災。当時、被災した明石市立天文科学館の大時計がキャンパス内に設置されています。本学が地域の共有財産として保存していくことを目的に明石市から譲り受けました。その記憶を永久に風化させないという願いを込めて、11号館の前で新たな時を刻んでいます。 |
「健康科学」「地域に生きる」「総合大学としての連携」。その3つを具現化していく核となるのが、総合リハビリテーション学部です。高齢化という社会テーマに、大学としてどのようにかかわり役立つことができるのか。地域の人々の暮らしの中でいかに貢献することができるのか、という視点から構想されました。
基本理念は「地域リハビリテーション」。それは「障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全に、生き生きとした生活が送れるよう医療や保健および生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動」のことです。ここでいうリハビリテーションとは、「機能の回復訓練」とのみ理解されているような「矮小化されたリハビリテーション」ではありません。この言葉のもつ本来の意味《全人間的復権》の思想と、その具体化を目指す総合的かつ統合的な社会的プロジェクトをさしています。
総合リハビリテーション学部は、職業等の専門領域を超えた有機的連携と協働が可能な「ヨコ割りシステム」実現を目指し、その中で活躍できる人材を養成します。医学リハビリテーション系と社会リハビリテーション系の独自性を保ちながら、理系文系の枠を超えて一体となり、相互交流と理解が図れる教育・研究体制を構築していきます。この取り組みを実現することにより、わが国が直面する高齢者・障害者・生活障害者にかかわる諸問題の解決が飛躍的に進むと確信しています。
|
|