脱炭素社会を実現する経済的な仕組みを研究


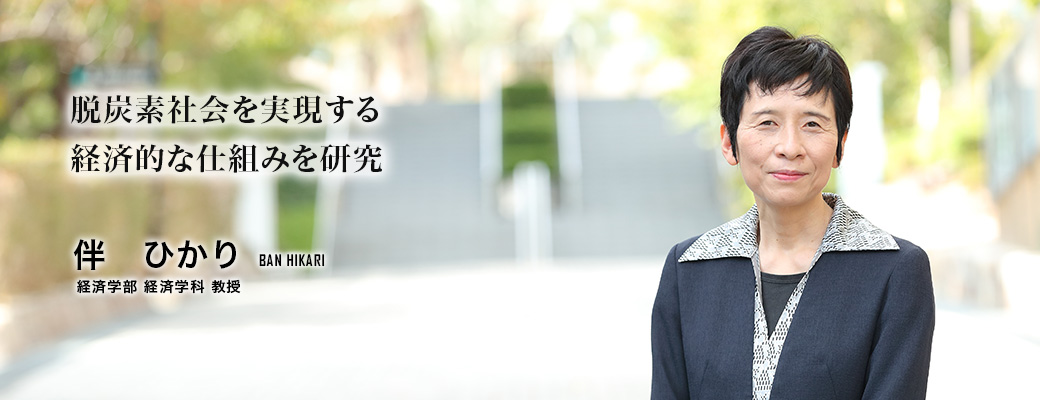
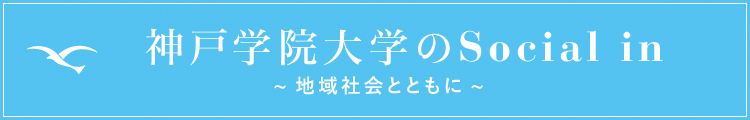

温室効果ガスを効率的に削減する排出量取引制度

今、地球規模で広がる気候変動が問題となっています。その主要因として指摘されているのが、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出量増加やCO2を吸収してくれる森林の減少です。産業革命以来進展した工業化や開発による森林破壊が、地球温暖化や気候変動を引き起こしているのです。2015年、気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定で、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて+2℃より十分低く保つとともに、+1.5℃に抑える努力を追求すること」「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源等による除去量との間の均衡を達成すること」という目標が定められました。その実現に向け、日本を含めた世界各国で2050年までにカーボンニュートラル、つまり温室効果ガスの排出量から植林や森林管理による吸収量等を差し引いた純排出量をゼロにするという目標が掲げられ、取り組みが進んでいます。
温室効果ガス排出量を効率的に削減する仕組みとして導入されてきたのが排出量取引制度です。1997年に採択された京都議定書でも取り入れられており、EUや中国・韓国では国・地域レベル、アメリカやカナダには州レベルの取引市場があります。日本でも東京都と埼玉県で実施されています。温室効果ガスは工業生産やエネルギー消費など経済活動によって排出されるものであり、経済活動を進めながら削減するにはどうしてもコストがかかります。例えば、火力発電に頼っていた電力を水力、太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーに代替していくための費用もその一つです。排出量取引制度は、国や企業が排出できる温室効果ガス量を排出枠として定め、排出枠市場で売り買いできるようにしたものです。国や産業、企業によって排出量の削減コストには違いがあるため、削減コストの低いところが大きく削減して排出枠の余りを市場で売却して利益を得る、削減コストの高いところは排出枠を市場から購入して削減コストを節約するといったことが可能になります。社会全体としてみれば、排出量を削減するための経済的な負担を軽減することが期待でき、削減しやすいところから削減を進めることでより効率的に排出量削減を促進できるメリットがある制度です。
私が排出量取引の研究に最初に取り組んだのは、2009年から2010年にかけて、「日本の脱炭素社会とポリシーミックスの提案」をテーマにした共同研究に参加した時です。エネルギー多消費型産業を対象に、国内排出量取引やCO2排出量に応じて税金をかける炭素税など各制度のもとでCO₂排出量削減のシミュレーションを実施し、国内排出量取引がその他の制度より効率的に排出削減ができるといった結果を導きました。
データを使って経済動向をシミュレーション

グローバル化した現代経済ではあらゆる分野で国際分業が進み世界中の国や地域が密接につながり合っているため、環境問題についても自国のことだけを考えるのでは不十分です。CO₂排出量削減においては、国内の生産活動(言い換えればエネルギー消費)によって排出されたCO₂量を対象とする生産基準だけでなく、他国で生産したものを購入して消費する場合、その過程で排出されたCO₂量も対象に含める「財の消費基準」という考え方が取り入れられるようになりました。例えば、日本が中国製品を輸入したとすれば、中国国内で生産時に排出されたCO2量を日本の消費基準排出量に含めるということです。
生産基準での炭素削減政策では、対策を行った国ではCO₂排出量が減少しますが、一方で対策を行わない国の製品が相対的に安くなって国際競争力を持ち、生産量が増加することでCO₂排出量も増加してしまう可能性があります。それを防ぐ意味でも、輸入国が消費基準で炭素削減政策を行ったり炭素税をかけたりする必要があります。国際分業に関心があった私はこの消費基準のCO2排出量という考え方に大いに興味を持ち、炭素削減政策や貿易自由化が消費基準のCO₂排出量の構造にどのような影響を与えるかといった分析を行っています。
私が研究に用いる分析手法は応用一般均衡モデル(CGEモデル)と呼ばれ、経済理論を基礎にした方程式と現実のデータによって経済の姿を記述するモデルの一つです。連立方程式によって記述された経済モデルのなかで、政策変数を変化させてシミュレーションすると膨大な結果が得られますが、それを丹念に分析すると多くのことが見えてきます。もちろんモデルもデータも様々な制約があるのでモデルが計算した政策の効果は慎重に解釈する必要がありますが、これまで変化の方向しか推測できなかったことを具体的な数値(大きさ)として捉えられるというメリットがあります。実際の経済政策の策定に活用されるのは言うまでもありませんが、大げさに言うと、近年重要視されている「業務の見える化」につながる分析手法です。
影響力の大きな中国の炭素削減政策を研究
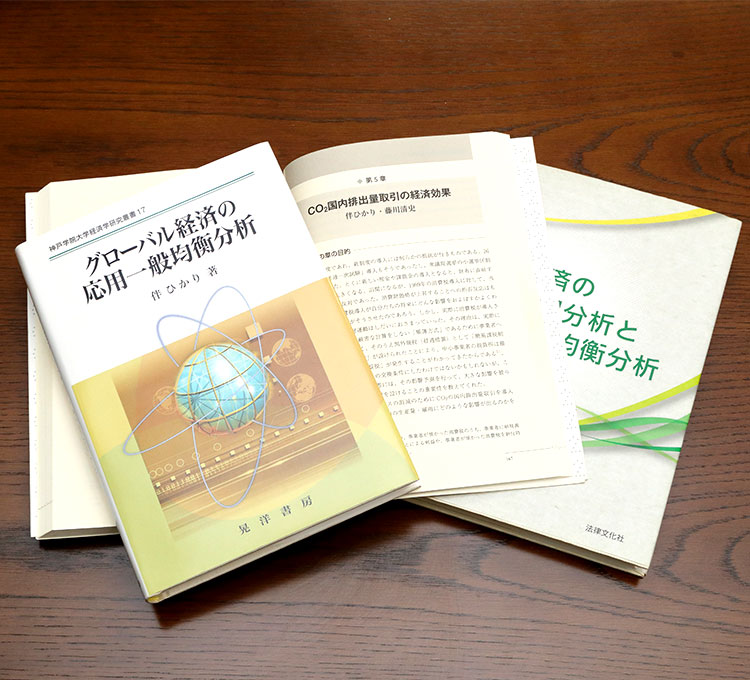
今後も、研究を通じて脱炭素社会に向けた知見の蓄積に少しでも貢献していければと思っています。現在は、世界経済に大きな影響を与える存在になった中国のCO₂排出量取引についても研究しています。中国は今、経済の急成長期を過ぎてCO₂排出削減の方向へと舵を切り、昨年から電力部門だけですが、中国全土をカバーする世界最大の排出量取引の市場が運用されています。今後は電力部門以外にも拡大する計画であり、どのような部門が排出量取引に参加するとよりCO2削減効果や経済効果が高まるのかといったことも研究テーマにしています。また、中国では不要になった石炭火力資本を他国に投資するという動きも活発になってきているため、そうした動向による環境や経済への影響も分析しています。
経済学は、様々な要素が複雑に絡み合った現実を精緻に分析できる応用一般均衡モデルのような手法を開発してきましたが、同時に、シンプルでありながら肝心なことを教えてくれる学問でもあります。私は学生時代、恩師が「経済原論」の授業中におっしゃった「私がこんなふうに講義をして生きていくことができるのは、他の人が必要なものを作ってくれているからです」という言葉を聞き、目からうろこが落ちる思いをしたことがあります。私たちは他の人の労働によって様々なものを消費し豊かさを享受できているということに改めて気づかされ、それをきっかけに分業に関心を持ったことが今に至る研究活動の原点です。
経済学は、全体像を理解するのに時間がかかるので、とっつきにくい学問ではありますが、経済学の基礎知識は学生が社会の一員として力を発揮するのに役立ちます。学生はもちろん社会人の方々にももっと経済学への関心を持ってもらえるよう、その面白さや重要さを伝えていくことができればと思っています。
Focus in class
-授業レポート-

グローバル経済の中で私たちの生活は、気候変動問題、新型コロナウイルス感染症の流行など世界共通の課題や、ロシアのウクライナ侵攻などの世界情勢に否応なく大きな影響を受けています。為替の変動やそれに伴う物価変動なども国際経済と密接にかかわるテーマです。私が担当している経済政策や国際経済学の授業の中でもそのような問題を取り上げ、学生に現実の経済の動きを論理的に理解してもらうようにしています。それを通して、自分の身の回りで起こっていることの原因を考え、自分が生きている社会が経済社会であるという意識を高めてほしいと思います。さらに、社会の一員として何ができるかを考えられる人に育ってほしいと考えます。
プロフィール
- 学歴
| 1987年3月 | 神戸大学 経済学部 卒業 |
|---|---|
| 1989年3月 | 神戸大学大学院 経済学研究科 経済学・経済政策専攻 博士前期課程 修了 |
| 1992年3月 | 神戸大学大学院 経済学研究科 経済学・経済政策専攻 博士後期課程 単位取得満期退学 |
- 経歴
| 1992年4月 | 神戸学院大学 経済学部 講師 |
|---|---|
| 1995年4月 | 神戸学院大学 経済学部 助教授 |
| 1996年5月 | Master of Arts Johns Hopkins University |
| 2007年4月 | 神戸学院大学 経済学部 准教授 |
| 2008年4月 | 神戸学院大学 経済学部 教授 |
| 2012年3月 | 博士(経済学)神戸大学 |
| 2017年4月 -2019年3月 |
神戸学院大学 経済学部 学部長 |
| 2017年6月 | 名誉博士 ウクライナ国立農業科学アカデミー・アグロエコロジー環境マネジメント研究所 |
