第5回「森わさ賞」受賞者、兵庫県栄養士会会長の橋本加代さんインタビュー
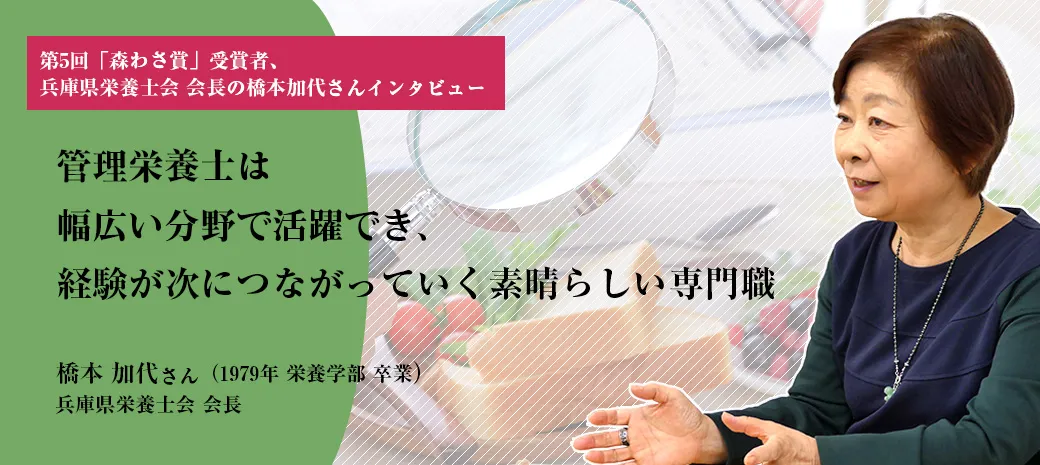
学校法人神戸学院の原点は、1912(明治45)年に創立された私立森裁縫女学校です。
その理念は、「艱難 (かんなん)にくじけず自活していける女性」と「真に社会に役立つ人間」の育成にありました。
神戸学院大学では、校祖である森わさ先生の志を継承し、研究・教育や社会において活躍する女性の教職員・卒業生・修了生を顕彰する「森わさ賞」を2019年度に創設。第5回「森わさ賞」に輝いたのは、1979年に栄養学部を卒業された10期生、兵庫県栄養士会会長の橋本加代さんです。ご自身の歩みや管理栄養士の役割などについて、お話をうかがいました。
プロフィール
兵庫県栄養士会 会長
橋本 加代さん
(1979年 栄養学部 卒業)
北摂中央病院で管理栄養士として患者の栄養管理を担当。1981年から兵庫県社保健所健康課をかわきりに県行政栄養士として10年以上にわたり県民の健康を守る施策に従事。退職後は管理栄養士養成施設で後進を指導。2010年以降は兵庫県栄養士会の広報など運営に関わり、2022年から現職。
病院や行政、フリーランスでの管理栄養士を経験し、養成機関の教員へ
「森わさ賞」受賞、おめでとうございます。一報を受けられたとき、どうお感じになりましたか。
まず、とても驚いたのですが、名誉ある賞をいただけて光栄です。同窓会の会報誌やホームページを見た同窓生たちからも連絡をもらい、嬉しかったですね。森わさ先生については高校(神戸学院女子高等学校、現:神戸学院大学付属高等学校)時代によく聞いていたので、懐かしく思い出しました。「報恩感謝」と「自治勤労」という森わさ先生からの校訓は、今でも覚えています。恩に報いなさい、常に感謝の気持ちを持ちなさい、社会のために貢献しなさいという教えが、自分自身にも染みついていたように思います。
そもそもどういった経緯で、神戸学院大学の栄養学部に進まれたのでしょうか?
自立するためには、手に職をつけておくことが大事だという思いが根底にあったため、何かライセンスを取ろうと考えたなかで、興味を持ったのが管理栄養士でした。私たちの時代は国家試験がなく、厚生労働省が認めた養成課程を経て、大学を卒業すれば資格を得ることができました。修得しなければならない単位も多く、卒業するのも難しかったのですが、授業は面白かったですし、勉強も頑張っていました。
卒業後のご経歴についても教えてください。
兵庫県西宮市にある北摂中央病院に入職し、患者さんたちの栄養管理を担当しました。現在93歳になる管理栄養士の大先輩に、新しい病院ができるので行ってみないかと声をかけていただいたのがきっかけです。どういう機材や食器を入れて…という開院準備の部分から関わり、一から給食をつくりあげる経験をしたことが、自分にとって最もプラスになりました。管理栄養士はベテランの栄養部長と私の2人だけ。献立作成から、発注、調理、衛生管理と、一連の流れすべてを学び、基礎をつくっていただきました。
立ち上げの時点から関われたのは貴重な経験ですね。そこから次のステップに?
病院が遠かったこともあり、先述の大先輩の助言により公務員試験を受けて、兵庫県の行政栄養士になりました。出先機関である保健所と本庁、両方を経験したのですが、それぞれに面白い仕事でした。保健所では、肥満児や減塩の対策、検診の事後指導といった健康維持増進の事業や栄養調査などに携わったのですが、住民の方と直接お会いし、密接な関係を築きながら取り組むことができました。
本庁での仕事は、いかがでしたか。
栄養改善施策の企画・立案や運営が中心でした。県民の栄養・食生活の実態を把握し、その食生活はどうあるべきか、指針やプランを策定したり、県内にある病院や学校、福祉施設などでどんな給食を出すべきか、ガイドラインを作成したり。兵庫県の栄養行政をどんな方向へ持っていくかという、舵を取れるのが一番の醍醐味でした。また、病院の監査では、病院管理栄養士の経験が非常に役に立ちました。現場の実態がわかっていなければ、指導もできませんからね。あわせて10年以上にわたり従事しました。
なぜ公務員を退職されたんですか?
当時は子育てとの両立が難しかったんですよね。けれど育児がひと段落した頃から、それまでに関わった方々から声をかけていただくことが増え、フリーランスの管理栄養士として働くようになりました。代表的な仕事が、小児科や循環器内科など、クリニックでの栄養指導でした。また、市の非常勤職員として、独居の高齢者や生活習慣病の方などのご自宅を訪ねて一緒に買い物や料理をするなど、栄養指導にも携わりました。その際、歯科衛生士さんや保健師さん、ホームヘルパーさんなど、さまざまな職種の人と出会い、一緒に仕事をしたことが、自分の仕事の幅を広げるのに役に立ったと感じています。また、非常勤講師として短期大学などへ教えに行くこともありました。
多彩なご経験をもとに、後進の育成にも力を注がれたんですね。
その後、管理栄養士の養成課程がある大学に教員として就職したのですが、これもまた、93歳の先輩管理栄養士のおかげです。教育のやりがいを感じていたところ、自分はもう引退するからと引き継ぐことになりました。二つの大学で働いたのですが、一つめの大学では、主に給食経営管理論と実習を担当し、病院管理栄養士や病院監査での経験を生かせました。給食管理の実習室に設計から関わった際にも、実務経験が役立ちました。もう一つの大学では、公衆栄養学と実習を担当。これも行政管理栄養士の経験が生きています。それぞれの職場で経験したことが、次々につながっていき、ステップアップしていくことができました。

学生時代に管理栄養士の土台を築けたことが、実務にもつながっている
神戸学院大学栄養学部での学びで、印象に残っていることはなんですか。
献立作成の課題に苦労したことが記憶に残っています。なんらかのテーマが与えられ、エネルギー量やタンパク質量などの目標値に沿った1日分の献立を考えるのですが、とても厳しい先生で、数字だけ合っていても駄目。こんな料理の組み合わせはおかしい、朝昼晩のメニューや味のバランスが悪い、食品数が少なすぎる、給食施設で作りづらいなど、あらゆる指摘を受けました。そのおかげで病院の管理栄養士になったとき、実務に入りやすかったです。
学生時代の経験が、実践でも生きたんですね。
授業以外でも、カウンセリング研究会というクラブに所属していたことが大きかったです。管理栄養士は、相手がどんな人なのか、どんな思いをしているのかを丁寧に聞き出す必要があります。指導にあたってくださった心理学の先生方や部員と、話を傾聴し合う体験を重ねられたことが本当に良かったですし、栄養学部以外の学生さんと触れ合う機会が得られたのも成長につながりました。
同級生や先輩後輩、先生方とのつながりで助けられたことなどはありますか。
兵庫県庁で研修会を企画したとき先生方に講師をお願いしたり、指針やガイドラインをつくる際にも助言をいただいたりと、本当に助けられました。同窓生たちとは、「栄養学研究ネット」という組織でつながっています。2007年に、当時の栄養学部長だった合田(清)先生と一緒に立ち上げ、今も栄養学部が事務局です。年に二回は研修会や勉強会、講演会を、一回は情報交換会を開いて、全国に散らばっている会員と世代を問わず交流を楽しみながら切磋琢磨しています。

歴史ある栄養学部ならではの強みでもありますね。
食品メーカーや製薬会社、教育機関や行政など、皆さん全国各地でさまざまな職に就かれているので、それぞれの分野のお話が聞けて勉強になります。何か困ったときにも、同窓の先輩だと話しやすいですし、力になってもらえるので、今、栄養学部で学んでいる学生さんたちにも、卒業後、ぜひ参加してほしいですね。
人との出会いを大切に、食の立場から皆さんの健康づくりに貢献したい
現在はどういった活動をされているのでしょうか。
2010年からは兵庫県栄養士会の広報などに関わり、2022年からは会長を務めています。食と健康の専門職として、県民の健康増進、疾病の予防および生活の質の向上に寄与するという目的のためにつくられた会です。現在の会員は1600人以上。そのなかで会を運営し、行政など外部とつなげていく役割が私にはあります。さまざまな委員会や審議会に代表として出ていき、兵庫県民の健康づくりに意見を入れていく。行政や教育、医療に関わる専門職など、多職種の人たちと一緒に、兵庫県民の健康に関わっており、現在、48の外部員会や団体と連携している状況です。
どういった事業を手がけられているんですか。
大きな柱は二つあって、一つは会員の人たちの資質を向上させる事業です。栄養士ほど多様な分野で仕事をしている専門職は珍しい。しかも職場には定年があっても、管理栄養士というライセンスに定年はありません。厚生労働省の定める食事摂取基準や社会が抱える食の課題も変わっていきますので、卒業後も研鑽が欠かせないのです。生涯教育研修会やスキルアップ研修会など、さまざまな研修会を企画・開催しています。また、学生の方でも参加できる、兵庫県栄養改善研究発表会などの場も設けています。
もう一つの柱は何になりますか。
栄養改善・健康づくりや、疾病の重症化予防を推進する事業です。県民の皆さんが気軽に相談できる場所として、兵庫県を10の区域に分けて「栄養ケア・ステーション」を設置しています。クリニックでの栄養指導や訪問栄養食事指導、オンラインでの栄養指導や、市や町が催す介護予防教室やフレイル予防教室の講師など、依頼があれば適切な人を派遣しています。

皆さんの健康づくりを身近なところからサポートされているんですね。
厚生労働省は今、健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブというものを立ち上げています。産官学が連携し、誰一人取り残さない食環境づくりの日本モデルをつくろうと動いているのです。それを受け、兵庫県は47都道府県の中でトップを切って、フレイル予防をテーマに取り組んでいくことになりました。
お年寄りが要介護になるのを防ぐのは重要なことです。
実は兵庫県は全国の中で大腿骨の骨折率が一番高く、低栄養の高齢者も最も多いというデータがあります。寝たきりの要因をつくらないよう、産官学、特に食品の製造業者や流通業者、メディアを巻き込んで、食環境づくりを通じたフレイル予防に戦略的に取り組もうとしているところです。栄養士会では、たとえば食品業者がつくった減塩の食品を住民に紹介するなど、消費者との間を取りもつ役割をしようと準備を進めています。
なるほど。消費者に寄り添った取り組みを進められているのですね。
他にも、災害時の食に関する支援事業にも力を入れ、日本栄養士会災害支援チームの兵庫支部「JDA-DAT兵庫」を組織しています。参加するには、災害時の栄養支援をどうすべきか学ぶ、専門的なトレーニングを受けてもらう必要があり、そのためのサポートも行っています。さらには、阪神・淡路大震災を契機に設立した学生ボランティアネットワーク「V-net」の運営も支援しています。

栄養士会の会長を務めるにあたり、心がけていらっしゃることはありますか。
県民の健康づくりを進めるためには、会員の皆さんが気持ちよく活動できる体制を整えておかなければいけません。そのためにも委員会や理事会では、誰もがその思いや意見を言いやすい環境をつくるよう努めています。現在、県も国も目標としているのは、健康寿命の延伸です。みんなで会を運営して、食の立場から皆さんの健康づくりに貢献できればと願っています。
これまでのキャリアを振り返り、感じられることはありますか。
私がここまで続けてこられたのは、出会った人たちに引っ張ってもらったおかげです。管理栄養士だけでなく、さまざまな職種の人たちと関わり、その関係を大切にすることが重要だと感じています。多様な見方に触れ吸収していくと、人間性の幅も広がりますし、その人脈もどこかで必ず役に立ちます。一方で、食の専門家としてのプロ意識を保つことも大切です。これから管理栄養士をめざす皆さんも、人との出会いを大切にし、生涯にわたって自ら学んでいく姿勢を持ち続けてほしいと思います。
